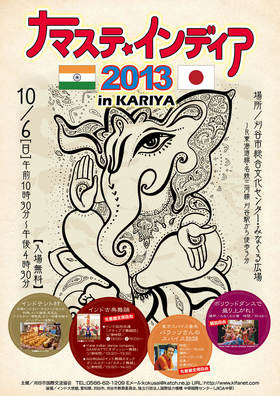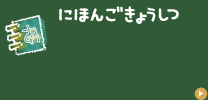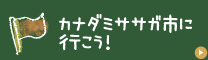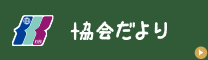2013.12.08外国籍住民のための無料健康相談会
市内や近隣地域に在住する外国籍住民の方を対象に無料健康相談会を開催しました。
○日時:12月8日(日)14:00~16:30
○場所:国際プラザ
NPO法人外国人医療センターをはじめ、刈谷医師会や刈谷市
歯科医師会の協力のもと、健康診断、歯科検診、レントゲン
検査、医師による問診など様々な検査が行われました。
通訳ボランティアの方々にもご協力いただき、英語、中国語、タガログ語、スペイン語、ポルトガル語に対応。

日本語のわからない外国人の方も自分の健康状態を知ることができ、抱えている健康上の悩みなど熱心に相談していました。そして、こういった機会があるのはとても助かると言っていました。
生活環境や言葉の壁などで普段なかなか健康診断などを受けられない外国人の方は大勢いると思うので、こういった活動をもっとたくさんの人に知っていただければ、より安心した生活を送ることができるのではないかと思います。




■当日の様子は、外国人医療センター(MICA)の活動ブログにも掲載しています。
当日お手伝いしてくれたボランティアさんのコメントも載っているので、是非ご覧くださいね。