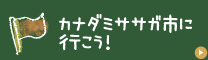【2025.01.25】KIFAボランティア研修会「多文化社会のコミュニケーション」
刈谷市国際交流協会では、毎年ボランティアのスキルアップを目的とした研修会を開催しています。今年のテーマは「多文化社会のコミュニケーション ~マイクロアグレッションを考える~」です。まずはマイクロアグレッションの概念を知り、多文化社会の中の一つのコミュニケーションスキルとして前向きに考える講義と、当事者として参加してくださったゲストスピーカー7人の体験談をもとにグループディスカッションをしました。
日時:2025年1月25日(土) 13:30~15:30
場所:国際プラザ
講師:塚本江美先生
(名古屋短期大学 英語コミュニケーション学科准教授)
今回のテーマである「マイクロアグレッション」は、英語の「小さな」という言葉と「攻撃」という言葉を組み合わせた造語で、「自覚なき偏見と差別」という意味合いで使われている言葉です。参加者のほとんどがこの言葉を聞いたことがないと答えていました。それは無理のないことで、この言葉と概念についての研究書がアメリカから日本に輸入され、翻訳本が出版されたのは2020年頃、つまり約5年前のことだそうです。そんな中、塚本先生がはじめにこの研修会の目標を次のように指し示しました。
①外国につながる人とのコミュニケーションを
より良くすること
→ 外国にルーツ・アイデンティティを持つ
人(多様な属性の人)との
より良いコミュニケーションを目指す
②自らが持つマイクロアグレッションに向き合う
→ 「自分も傷ついているのでは?
傷つけているのでは?」という
視点を知る/考える
そこからは、科学的な根拠やこの概念が現れた時代背景と変遷を少し学術的なお話も交え、さらに具体的にマイクロアグレッションとは何かを紐解いていきました。衝撃的だったのは、マイクロアグレッションの日常的な蓄積が心身の健康被害を引き起こすというものでした。1時間の講義の後に、各グループに配置されたゲストスピーカーのみなさんに、話せる範囲でそれぞれのマイクロアグレッションの体験を話していただきました。ここで耳にした貴重な生の声は、参加者みなさんの心に届いたようでした。それは個人的な経験でもあり、様々な物語や背景、宗教や文化・慣習に因るものなので、こうした具体的な事例に対して、ではどうすれば良いのかについてもグループ内で話し合い、最終的にどんなディスカッションだったのか全グループで共有しました。
結論は「簡単な解消方法はない」としても、この研修会の目的「より良いコミュニケーションを目指す」ためには、コミュニケーションに対し萎縮・躊躇があってはならないと感じました。塚本先生の資料では下記のようにまとめられています。
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
〈嫌なことは嫌であると勇気をもって伝える〉
〈気づかずに言ってしまったら、その軽率さを謝ろう〉
〈故意であってもなくても傷ついている人を見つけたら、
寄り添う〉
〈コミュニケーションを諦めない〉
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
研修会を終えて、ゲストスピーカーと参加された方々から前向きな意見が届いてきています。デリケートなテーマではありましたが、みなさんの反応から今回の研修会はとても有意義だったと実感しました。また今回参加できなかった方々にも今後このような機会があれば是非、耳を傾けて一緒に考えていただきたいと思いました。理解したこと・学んだこと・感じたことを活かして、ボランティア活動のみならず様々な場面に役立ててくださることを切に願っています。
「マイクロアグレッション」という概念が世間一般で見聞きするようになる時、塚本先生がおっしゃるように「他者を思いやる人間関係が、社会も自分も幸せにする」
そんな多文化社会であってほしいと思います。